退職したいと言いにくい時はどうすればいい?
こういった疑問に答えます。
- 看護師が退職したいと言いにくい原因・よくあるトラブル
- よくあるトラブルへの対処法
- 退職したいと言いにくい時にやるべきコト
勇気をだして退職を切り出したおかげで、地獄のような病院勤務から抜け出せ、今は一般企業で働けるようになりました。
「看護師を辞めたいけど、トラブルが怖くて退職したいと言いにくい…」その気持ち痛いほどよくわかります。
なぜなら私も「人手不足のなかで辞める申し訳なさ」や「強い引き止めへの不安」「師長から嫌味を言われるかもしれないという恐怖」などから、なかなか退職を切り出せなかったから。
退職を切り出せないなか辞めたい意思を伝え、無事に退職できたのは、覚悟を決め未来を重視したのが大きいです。
今回はそんな私の実体験にもとづいて、看護師が退職したいと言いにくい原因やよくあるトラブルへの対処法、退職したいと言いにくい時にやるべきコトなどについて解説していきます。
看護師が退職したいと言いにくい原因・よくあるトラブル

安心してください。「トラブルが怖くて退職したいと言いにくい…」という悩みを抱えているのは、あなだではありません。
多くの看護師があなたと同じ悩みを抱えて、退職を切り出せずにいます。
では、看護師が退職したいと言いにくい原因には、どんなものがあるでしょうか。よくあるトラブルとあわせて紹介します。
- 強い引き止めにあう
- 奨学金の一括返済を求められる
- 師長からの悪意ある口撃
原因①|強い引き止めにあう
強い引き止めは看護師の退職時によくあるトラブルの一つで、退職したいと言いにくい現状をつくりだしている原因にもなっています。
強い引き止めにあう原因としてとくに多いのが、人手不足を理由とした引き止め。
実際、強い引き止めにあった看護師の声をみてみると、
などの声が。人手不足を理由に強い引き止めにあっている現状や、強い引き止めが退職したいと言いにくい現状をつくりだしていることがわかります。
わたしも人手不足を理由に強い引き止めにあい、退職を一旦断念。退職できたのは、退職を伝えてから半年以上たってからでした。
原因②|師長からの悪意ある口撃
退職したいと言いにくい現状をつくりだしているのは、師長からの悪意ある口撃が原因である場合もあります。
実際、師長からの悪意ある口撃を恐れている看護師の声をみてみると、
などの声が。師長からの悪意のある口撃が、退職したいと言えない現状をつくりだしていることがわかります。
わたしが退職するときも「ここまで育てた恩を忘れたの!」「あなたなんてどこに行っても通用しない!」という口撃をうけました。
悪意ある口撃に心折れず無事に退職できたのは、絶対に退職するという強い意志をもっていたのが大きいです。
原因③|奨学金の一括返済を求められる
奨学金が原因による退職トラブルも、退職したいと言いにくい現状をつくりだしている一つの原因に。
実際、奨学金が原因による退職トラブルを抱えている看護師の声をみてみると、
などの声が。奨学金の存在が、退職したいと言いにくい現状をつくりだしていることがわかります。
退職したいと言いにくい看護師必見!よくあるトラブルへの対処法

では、トラブルが怖くて退職したいと言いにくいときは、どうすればよいのでしょうか。
ここではよくあるトラブルである強い引き止めや悪意ある口撃、奨学金問題への対処法について紹介します。
- 円満退職を諦める
- 悪意ある口撃への心構えをしておく
- 退職するという強い覚悟をもつ
- 前向きな退職理由を伝える
- 人員補充しやすい時期を退職日する
- 奨学金を返済中の場合は契約内容を確認する
対処法①|円満退職を諦める
「トラブルが怖くて退職したいと言いにくい…」という状況を打開するためには、はじめから円満退職を諦め、トラブルへの備えをしておくことが重要。
たとえば強い引き止めがあることを想定しておけば、強い引き止めへの備えができますし、奨学金の返済問題があることを想定しておけば、奨学金問題への備えができます。
備えあれば憂いなし。万が一に備えて、前もって準備しておけば、なにか起きたときの心配事をなくせます。
とくに看護師の退職ではトラブルがつきもの。
「トラブルが怖くて退職したいと言いにくい…」という状況を打開するためにも、はじめから円満退職を諦め、トラブルへの備えをしておきましょう。
対処法②|悪意ある口撃への心構えをしておく
あなたの退職は師長にとってマイナス要素。とくに、慢性的な人手不足が続く現場ならなおさらです。
退職の意思を伝えた途端に、感情的に責め立てられたり、悪意ある口撃を受けたりすることも…。
退職の意思を伝えるときは、冷静に聞き流す準備をするなどして、悪意ある口撃への心構えをしておきましょう。
また、悪意ある口撃ばかりで退職の話がすすまないと判断したら、伝える相手を師長から部長に変更する必要もあります。
重要なのは師長の悪意ある口撃を真に受けないこと。悪意ある口撃は聞き流し、退職するという目的を達成するために冷静に行動しましょう。
対処法③|退職するという強い覚悟をもつ
少しでも退職に迷いがあると「強く引き止めればなんとなる」と師長に思われてしまう危険が。
強い引き止めにあわないためには、退職するという強い覚悟をもつこと、退職の意思をしっかりと伝えることが重要です。
退職の意思を伝えるときは「退職したいと思っています(相談)」ではなく「退職させていただきます(決断)」と伝えるようにしましょう。
退職の相談をすると退職に迷いがあると思われてしまい、引き止めにあう可能性が高くなりますが、退職決断の意思を伝えることで、引き止めにあう可能性を下げられます。
強い引きとめというトラブルを回避するためには、強い引き止めにあわないようにすることが重要。
退職するという強い覚悟をもって、はっきりと退職の意思を伝えましょう。
対処法④|ポジティブな退職理由を伝える
ネガティブな退職理由(人間関係や待遇への不満など)を伝えると、強い引き止めにあう確率が上がってしまいます。
退職理由を伝えるときは、ポジティブな退職理由を伝えて、強い引き止めにあう確率を下げましましょう。
ポジティブな退職理由には、以下のようなものがあります。
- 語学留学のために転職したい
- スキルアップのために転職したい
- 看護師以外の仕事を経験するために転職したい
- 本当にやりたいことを実現するために転職したい
- 今の病院ではできないことを経験するために転職したい
退職理由を伝えるときは、師長からの質問に答えられるように、ある程度の下調べをしておくことが必須。
たとえば「今の病院ではできないことを経験するために転職したい」を退職理由にする場合は、転職先をいくつかピックアップして、転職先の特徴や転職先でできることなどを調べましょう。
転職先についての情報収集をするときには、自力での検索だけでなく、看護師転職サイトの活用もオススメ。
看護師転職サイトを活用すると、
- ネットにはのっていない情報
- 転職エージェントしか知らない内部情報
など転職先のリアルな情報を得られる可能性があります。
強い引き止めにあう確率を下げるためには、退職理由の信ぴょう性をアップさせることが重要。しっかりと情報収集を行い、師長からの質問に答える準備をしておきましょう。
なお「強い引き止めにあわないため」という目的を達成するためには、多少の嘘も致し方なし…。
想像の世界でもいいので、ポジティブな退職理由をしっかりと考えて、師長との退職交渉にのぞみましょう。
対処法⑤|人員補充しやすい時期を退職日する
強い引き止めを避けるためには、人員補充しやすい時期を退職日に設定するのが重要。
人員補充しやすい時期での退職なら、あなたが退職した後の人員をうめられる可能性が高くなるため、人手不足による強い引き止めを避けられやすくなります。
もっとも人員補充しやすい時期は「4月」。
年度はじめである4月は、1年のなかでもっとも人の流れが活発になるため、他の月に比べて人員補充がしやすくなります。
強い引き止めを避けるためにも「4月」を退職時期に設定するのがベスト。
とはいえ、今すぐに退職したいと思っている人もいるはず。
今すぐに退職したい場合は、強い引き止めを覚悟したうえで、
- 退職するという強い意思をもつ
- 前向きな退職理由を伝える
など強い引き止めに負けない対策をたてて、退職交渉にのぞみましょう。
対処法⑥|奨学金を返済中の場合は契約内容を確認する
奨学金を返済中の場合で「奨学金を一括返済しないと退職させない」と言われても、退職することは可能です。
というのも、奨学金の返済を理由に引き止めを行うこと(経済的な足止め)は、労働基準法第16条で禁止されているから。
ただし、退職しても奨学金の返済義務がなくなるわけでないので、
- 一括払いではなく分割払いにしてもらう
- 別の病院で働きながら返済できるようにしてもらう
- 転職先の病院にたてかえてもらう
など方法で奨学金の返済をおこなう必要があります。
奨学金についての取り扱いについては、職場によって異なるため、まずは契約内容の確認をしましょう。
なお「奨学金の返済を理由に退職させてくれない…」「一人ではどうしても解決できない…」という状況が続いている場合には、わたしNEXTなどの退職代行サービスに相談するのも一つの手。
退職したいと言いにくい時は先に転職先を決めることも重要

退職したいと言いにくい状況を打破するためには、よくあるトラブルへの備えをするだけでなく「退職前に転職先を決め」強制的に退職せざるを得ない環境をつくることも重要。
強制的に退職せざるを得ない環境をつくることで、退職への踏ん切りがつき、退職したいと言う決心がつきやすくなります。
さらに、退職前に転職先を決めておけば、退職から転職までの間隔をあけずに、次の職場で働けるようになり「貯金がない場合」や「次の転職先が見つかるか不安な場合」でも安心して退職できるように。
なお、転職先を決めるときは、看護師転職サイトの活用して、転職先のリアルな様子を知ることが重要。
転職先のリアルな様子を知ることで、新しい職場・環境で働く不安を軽減できます。
実際、看護師転職サイトを活用すると、
- 比較検討できる求人数が増える
- 希望する求人を探してくれる
- 内部情報をゲットできる可能性がアップする
- 職場見学のセッティングをしてもらえる
など多角的かつ網羅的に情報収集することが可能に。
とくに転職先のリアルな様子を知るためには「職場見学」が必須。とはいえ「見学だけをさせてほしい」という連絡をするのはけっこうハードルが高いですよね。
一方で、看護師転職サイトを活用すれば、転職エージェントがあなたの代わりに職場見学のセッティングをしてくれるので、ストレスフリーで情報収集をおこなえます。
なお、わたしが実際に利用したよかった看護師転職サイトは、以下の3つ。
| 転職サイト | 求人数 | HP | |
| 1位 | レバウェル看護 (看護のお仕事) | ◎ | ◎ |
| 2位 | マイナビ看護師 | ◎ | ○ |
| 3位 | ナースパワー | ○ | △ |
看護師転職サイトの選び方や、オススメの転職サイトの詳細については「【転職経験者が厳選】看護師転職サイトランキングTOP3を紹介!」で詳しく解説しているので、参考にしてもらえたらうれしいです。
【まとめ】退職したいと言いにくい時は辞めない事による損失を考えよう
 今回は、看護師が退職したいと言いにくい原因やよくあるトラブルへの対処法、退職したいと言いにくい時にやるべきコトなどについて解説してきました。
今回は、看護師が退職したいと言いにくい原因やよくあるトラブルへの対処法、退職したいと言いにくい時にやるべきコトなどについて解説してきました。
トラブルが怖くて退職したいと言いにくいときは、辞めないことによる損失(デメリット)と、辞めた後に得られる利得(メリット)を考えることが重要。
じっくりと考えたうえで、辞めないことによる損失(デメリット)の方が大きいと判断したら、勇気と覚悟をもって退職したいと伝えましょう。
>看護師におすすめの転職サイトを知りたい方はこちら!
>わたしNEXTの評判や口コミを知りたい方はこちら!
- 労働問題弁護士ナビ|看護師を辞めたい方へ!辞めたい理由別の対処法と退職・転職の手順

.002-640x360.jpeg)
.001-14-640x360.jpeg)
.001-640x360.jpeg)
.002-640x360.jpeg)
.001-2.jpeg)
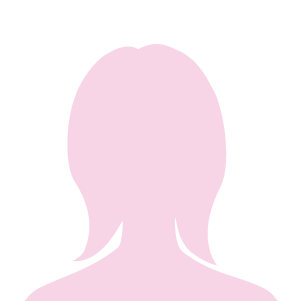

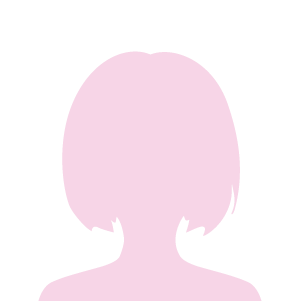
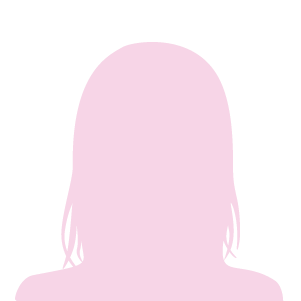


.001-320x180.jpeg)
.002-320x180.jpeg)
.002-320x180.jpeg)
.001-14-320x180.jpeg)